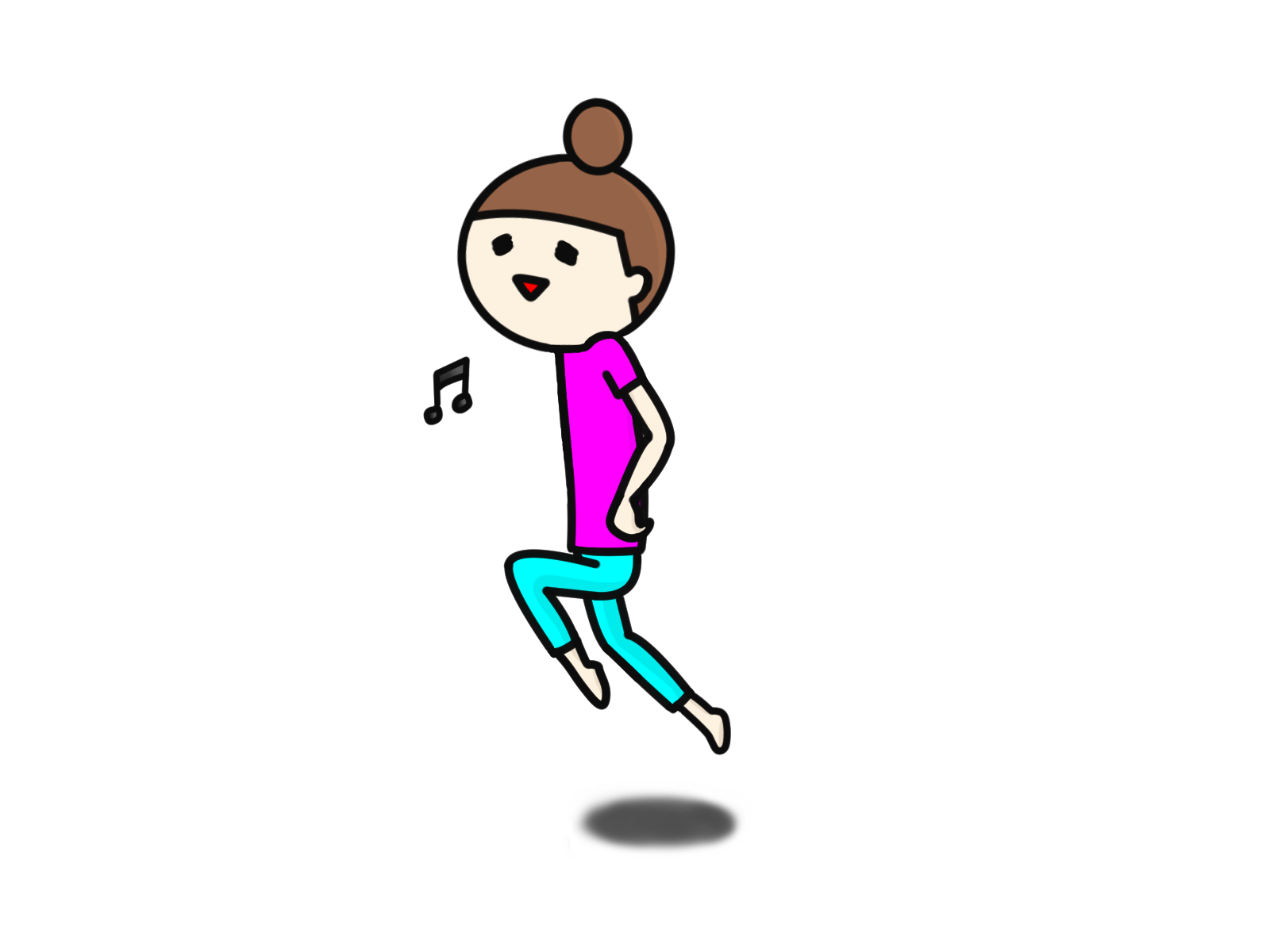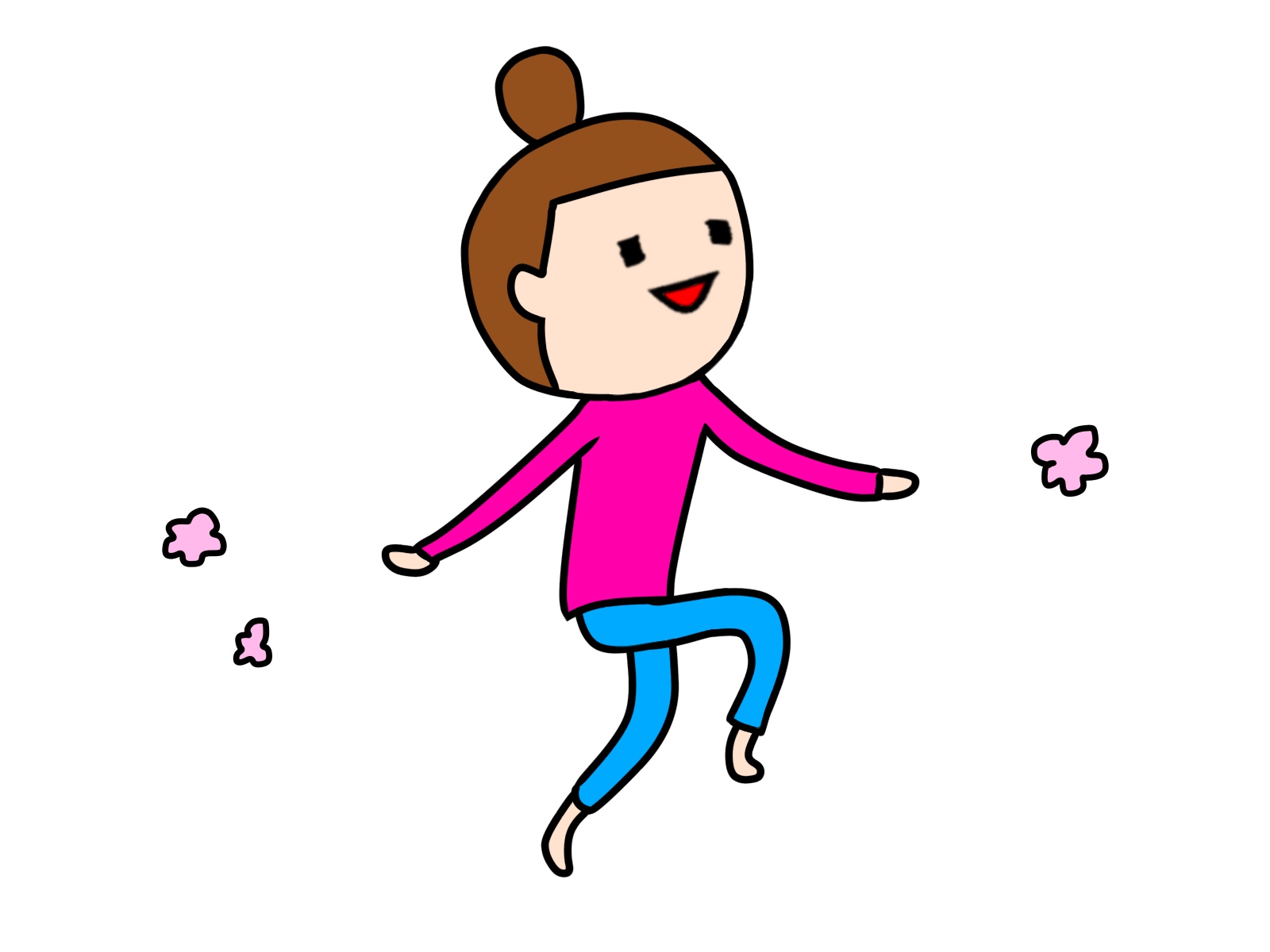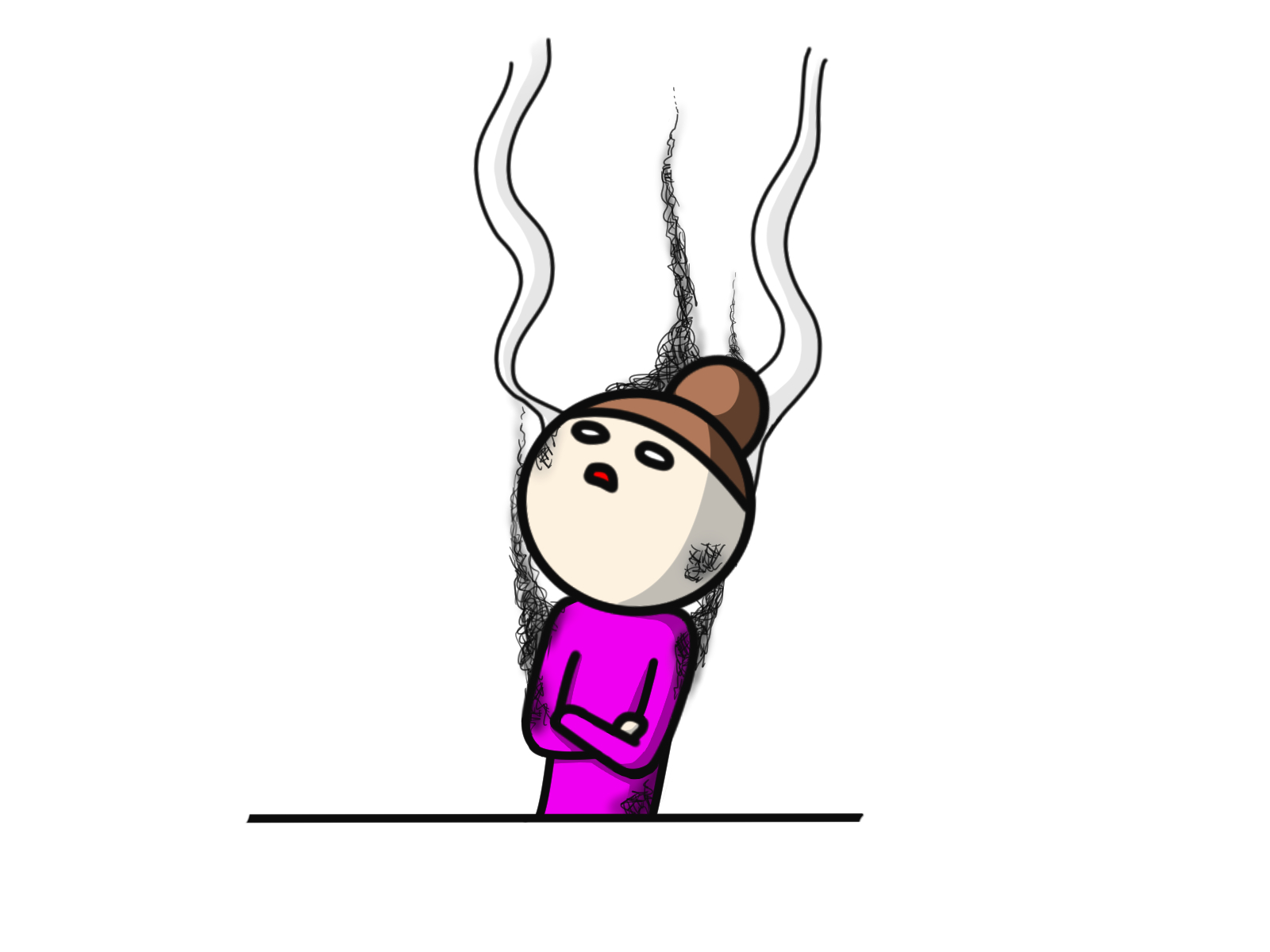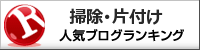タスク管理って言葉は、なんだかビジネスマンみたいなイメージだった。
でも、育児中の親こそタスク管理が有効なんだって!
タスクリストを幼稚園児に共有することで起こった変化や、リストに書かれたタスクを実行させやすくするポイントなどもまとめてみたよ。
Contents
タスクリストを書いて幼稚園児に渡した結果
家事育児をてきぱきとやるために、タスクリストにこだわってみようと思った。
昨日、この本を読んでみたんだ。
その名も、「マンガでわかる!幼稚園児でもできた!!タスク管理超入門」という本。

その名のとおり、タスク管理について書かれている本なんだけど、ぶっちゃけ、タスク管理すげぇというより、旦那さんが毎日子供と自分のお弁当づくりしているのがすげぇ!!
タスク管理の仕方自体は、なんかとりたてて目新しいことはないように思えたんだけど、幼稚園児にタスク管理をさせてみるという発想はなかったなぁ。
確かに、自分で自分のことやってもらえるなら、母としてはとても助かる!!笑
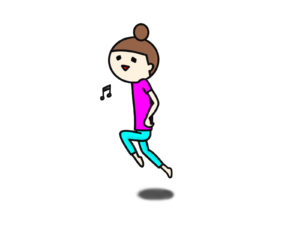
この本では実際に、幼稚園児の息子に対して、こういうリストを渡している。
○月○日(げつようび)
・あさおきたらやること
□トイレ
□ごはん
□はみがき、かおあらう
□きがえ
・もちものちぇっく
□ぴんくのぼうし
□うわばき
・かえってきたらやること
□てあらい、うがい
□にもつをだす
・あしたのようい
□コップ
□タオル
・・・
などなど、わかりやすく書いて渡してあげていた。
その結果、幼稚園児が自分で幼稚園の準備ができるように!!
幼稚園児にとっても「あれもこれも」と口で言われるより、あらかじめ書いてある方がわかりやすいんだな。
そしてさらに、準備しながら時間をはかることで、こどもも準備に何分かかるかがわかり、テレビを見る前などにやってしまうようになったらしい。
素晴らしい。

主婦が実行しやすいタスクリストの書き方は?
なんかこの本、ビジネスマンというより幼稚園児のいる親が読む方が絶対に有意義な気がする!
うちの息子はまだ1歳だから、「読んで理解する」ということができないんだけど、文字を読めるようになったらぜひ試してみたい。
マル子自身はというと、最近、バレットジャーナルをつけているので、簡単なタスクリストも日々作っているんだよね。
バレットジャーナルって何?というあなたは、こちらの「バレットジャーナルって何?メリットと効果について調べてみた」を見てほしい。

この「マンガでわかる!幼稚園児でもできた!!タスク管理超入門」の作者は、日常のありとあらゆることをタスク化して、いろんなルーチンも効率化させていた。
仕事だけでなく、日常に使えるというのが良いよね。
タスクをより実行しやすくするには、そのタスクをおこなうべき状況や行いやすい状況など、コンテキストを考えると良いらしい。
これ、あな吉手帳でも書いてあって、マル子はめっちゃこれで助かった記憶がある。
つまりどういうことかを例にだしてみるね。
- メールチェック
- 実家に置いてある息子の下着を1枚補充
- ブログを書く
- 「百姓貴族」を読む
こういうリストがあったとして、これを分析するとこうなる。
- メールチェック
⇒パソコンを開いてないとできない
- 実家に置いてある息子の下着を1枚補充
⇒実家に行ったときにやること
- ブログを書く
⇒息子が寝ているときにやること
- 「百姓貴族」を読む
⇒いつでもできること
こんなふうに、それぞれのタスクは、実行できるタイミングが異なる。
だから、このように分類する。
- 息子が寝ている間にやること
・夕飯の準備
・ブログを書く
・英語の勉強をする
- 実家でやること
・下着一枚補充
・北海道土産を持っていく
- 息子が起きていてもできること
・「百姓貴族」を読む
・一緒に英単語を覚える
・洗濯
その他、マル子の場合は「夫に頼むこと」「10分以内にできること」などの欄もある。
このように状況によってリストを分類していくことで、自分の状況に即したリストを解消していくことができる。

このようにコンテキストを意識してリストを作成すると、「今、何ができるか」が明確になって動きやすい。
その結果、息子を寝かしつけたままスマホでだらだら~もしなくなった。
正確に言うと、息子が寝ている間にやりたいことがたくさんあることを思い出して、スマホでだらだらするという行為の優先順位がかなり下がっただけなんだけど。
マル子の経験では、コンテキストを考えてリスクを作ると、実行するまでに脳に負荷がかからないからか、達成率が劇的に変わった。
リストを作っても実行できずにいるのであれば、是非試してほしい。
そう、「実行しやすくなること」がこういうリストではとても大事なんだと思う。
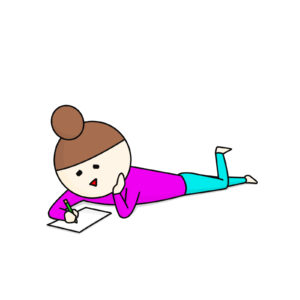
というか、実行しやすくするために、こういうリストを作っていくんだと思う。
「あれやらなきゃこれやらなきゃ、他に必要なことあったっけ・・・?」と思い出そうとすることで、脳にけっこう負荷がかかっちゃうじゃない?
それをなくすためにこういうタスクリストが存在するんだと思う。
で、さらに実行しやすくするために、より細分化したり、実行するタイミングをこうやって指定していくんだと思った。
タスクリストとToDoListはどう違うのか
そしてマル子が疑問に思ったのは、「タスク管理とToDoListの違いってなぁに?」ってところ。
調べてみたら、
・ToDoList⇒日付けが決められていないもの。
・タスク⇒期限が決まっているもの
というものらしい。

ははん、なるほどね。
ちなみにうちの夫にToDoListとタスクリストの違いを聞いてみたら、「ToDoListは自分でやること、タスク管理は他の人ふくめてやること?とか?」と言っていた。
そんな夫は今、1歳児に向かって圧力と面積の関係性について熱く語っている。謎。
どうやら、夫の中ではタスクとプロジェクトが一緒になっているらしい。
ちなみに、タスクは、「最小限単位のやること」にたいし、プロジェクトは「タスクの集大成」らしい。
うん、だんだんごっちゃになってきたけど、そんな感じ。

家事育児が捗るタスクリストの書き方!まとめ
やっぱり、幼稚園児が使いやすいタスクリストにしたことで、自分で自分の面倒を見られるようになったという変化が素晴らしい。
マル子も将来、ぜひつかわせてもらおうと思う。
こういうふうに状況別にリストを作ると、幼稚園児も大人もリストを実行しやすくなるんだね。
「あれやらなきゃこれやらなきゃ」って頭の中がパンパンになったときに、書き出すだけでもだいぶスッキリするよね。
けど、そこからさらに少しこだわることで、思った以上にやりやすくなるらしい。
これを踏まえて、毎日のタスクリストを作り直して試してみようと思った。
関連記事⇒バレットジャーナルって何?メリットと期待できる効果を調べてみた